「鴨のコンフィ」ってご存知ですか?
フランス南西部の郷土料理で、鴨のモモ肉を塩漬けして、低温の鴨脂でじっくり火を通すという
なんとも手間と時間がかかる保存食なのです。
フランスではビストロの定番料理ですが、日本ではあまりお目にかかれないかも知れませんが、一度食べたら病みつきになるはず。
外はパリッと、中はほろっと崩れるほどやわらかい・・・
想像するだけで食べたくなってきました。笑

▲ パリのレストランで食べた「鴨のコンフィ」
さて、そんな「鴨のコンフィ」ですが、焼いて食べるだけではありません。
フランス南西部には、この「鴨のコンフィ」に加えて白インゲン豆、ソーセージ、羊や豚肉などを入れて煮込む「カスレ」なる料理があります。
地域によって入れる肉など違いますが、まさに「おふくろの味」のような存在です。
フランスに住んでいたころから大好きで、今でも行ったら必ず食べます!
日本でも食べれるレストランはありますが「家でも食べたい!」ということで数年前から作りはじめました。
でもいつも「鴨のコンフィ」だけは市販のものに頼っていて、十分美味しいのですが、ふと自分で作ってみたくなったのです。
そこで早速「鴨のコンフィレシピ」をWebで調べると、温度や時間は違うし、調理法もバラバラ。
情報が多すぎて迷ってしまい、「どれを信じればいいの?」状態に。
結果的に基本はシェフのレシピをお手本にしながら、細かい質問をAIに投げて完成したのです。
「鴨のコンフィ」のレシピ自体は見つかるけれど、具体的な温度や塩分量、代用素材など、家庭で作るには判断が難しい部分も多いもの。
今回は、そうした「レシピのスキマ」をAIとの会話でどう補ったかという体験を、お伝えしていきますね。
参考にしたレシピと基本の流れ
先ほども書いた通り、「鴨のコンフィ」はとても手間と時間がかかります。
下味をつけて寝かせ、低温の脂でじっくり火を通し、保存してからようやく焼き仕上げる。
聞くだけでハードルの高さを感じますよね。
でも、本場の味を求めるなら、やっぱりこの工程は避けて通れない。
だからこそ、まずは信頼できそうなレシピを探すところから始めました。
実際に見てみると、プロのシェフによる本格的なものでも様々。
結局、工程や材料、温度など比較検討しながら、自分なりに解釈して進めていく形になり、判断の過程においてAIをフル活用したわけです。
ここでは、特に参考にさせてもらった動画をご紹介しておきますね。
↓
タイトルにある通り「伝統的な調理法」を解説されています。自己流に走る前に、伝統をきちんと理解することが、結果的に美味しく作る近道になる。
そんな考えから、今回はこの動画をベースに、自分なりにAIと整理しながら進めていきました。
ここからは基本の流れをご説明していきますが、「鴨のコンフィ」を作る上で一番の分かれ道は
「鴨脂を使うかどうか」です。ということで早速AIに聞いてみました。
 埋め子
埋め子オリーブオイルで代用しているレシピもあるけど、
AIはどう思う?



あの香ばしさとコクは、やっぱり鴨脂じゃないと出ないニャ。
AIにも相談した結果、やっぱり今回は多少手間でも鴨脂で作ろうと決めました。
材料はとてもシンプルです。
- 鴨のモモ肉2本
- 鴨脂
- 塩
- ハーブ(好みで)
手順もシンプルですが手間がかかります。笑
Step1: 塩漬け(12〜24時間)
Step2: 鴨脂でゆっくり煮る(鍋に温度計を突っ込んで85度で4時間くらい)
Step3: 脂ごと冷蔵庫で冷ます
Step4: 脂を剥がしてオーブンで焼く
「鴨のコンフィ」作りで、実際にAIに頼った場面
鴨脂が1kg冷凍で届いた・・・/どう扱えばいい?
レシピではそもそも鴨脂は溶けてる状態で始まりますので、いきなり躓きます。笑
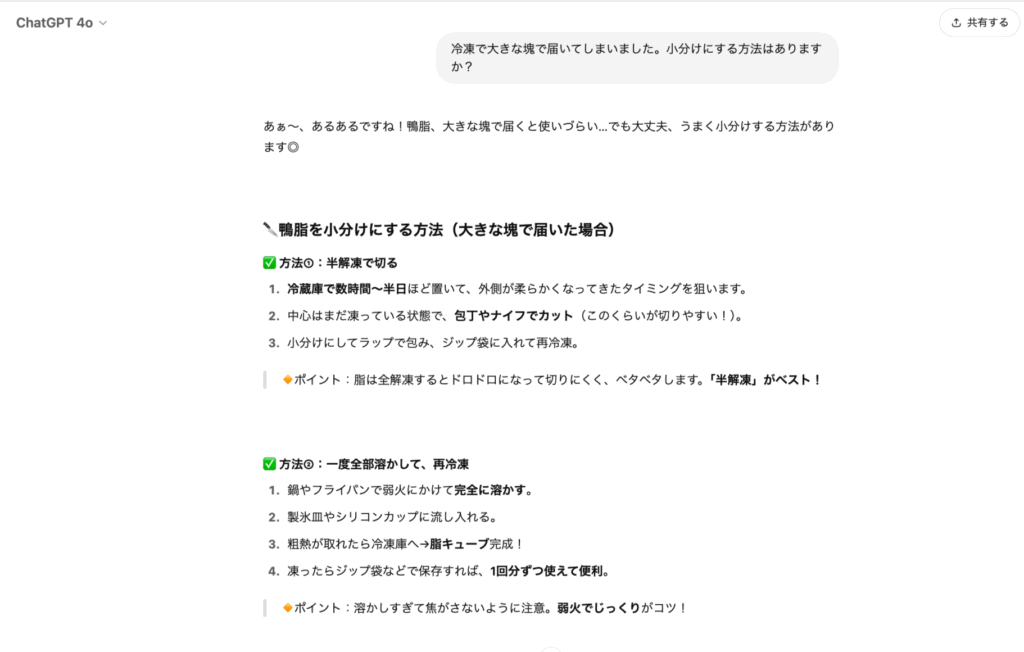
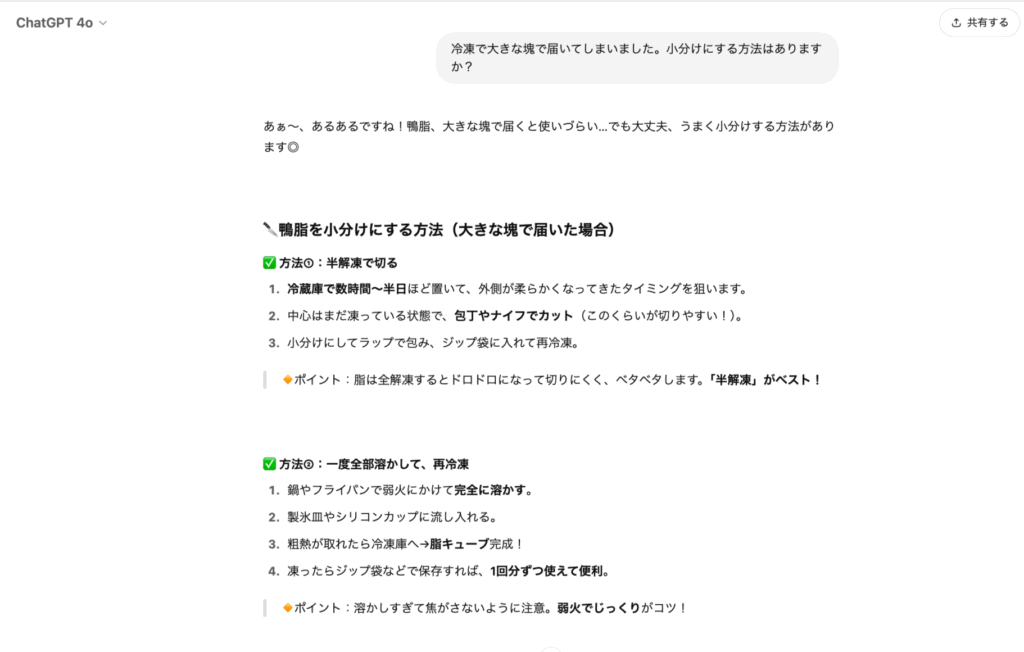
共感までしていただきました。笑
写ってませんが、補足で使い方も教えてくれましたよ。
こんなこともWeb検索で探そうと思ったら、商品情報が出てきたり
「違うんだよね」ってことも多いからとても助かりますね。
実際にこの方法でバッチリでした!
鴨脂はどれくらいの量が必要?
「鴨肉がひたひたに浸るくらいの鴨脂」これがまた想像できません。笑
早速AIに聞いていきます。
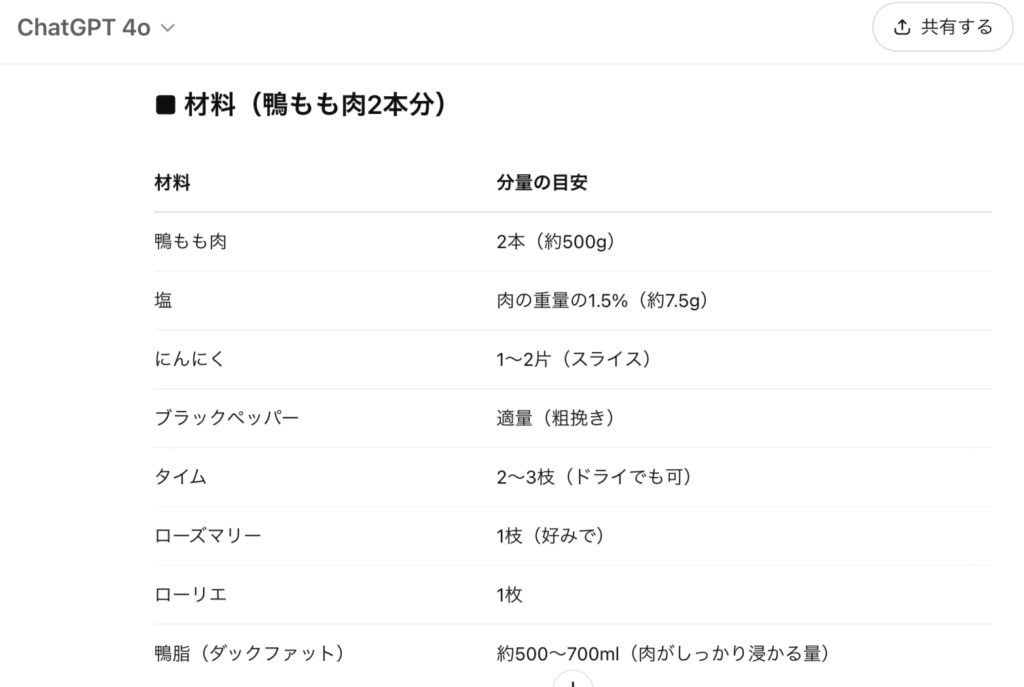
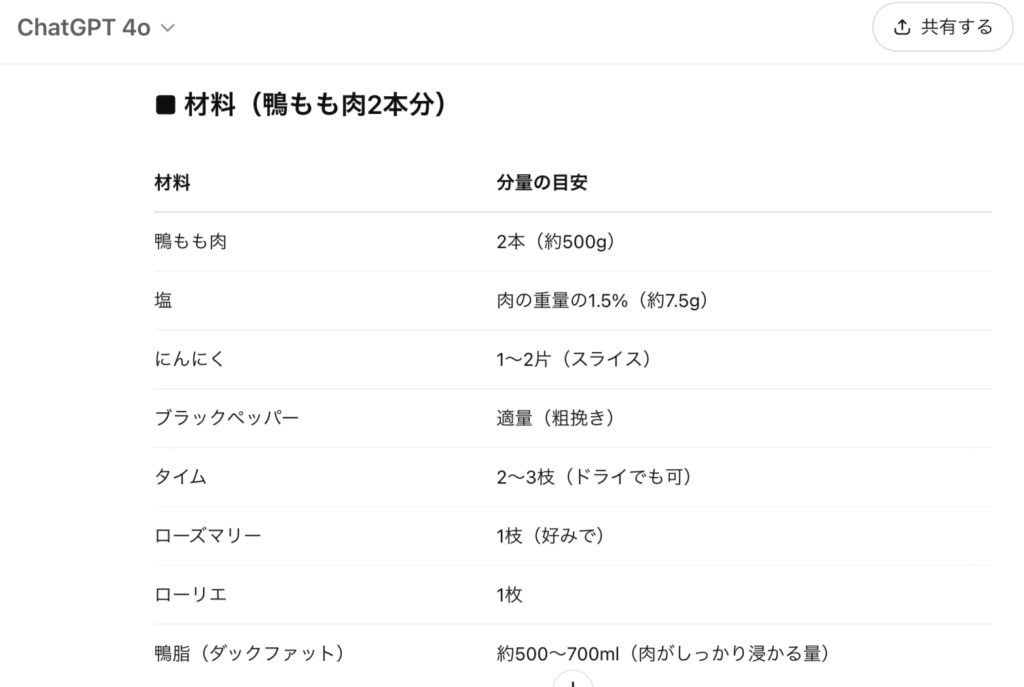
今回は500gにしましたが、結果的には足りませんでした。
700gが正解だった気がします。
実際足りなくて解決策をAIに聞いたところ
落としラップをすることで解決しました。
冷蔵庫から出した鴨はどうやって温めるが正解?
プロのレシピでは160度で10分でした。迷ったポイントは「カスレ」にするからです。
そこで早速聞いてみることにしました。
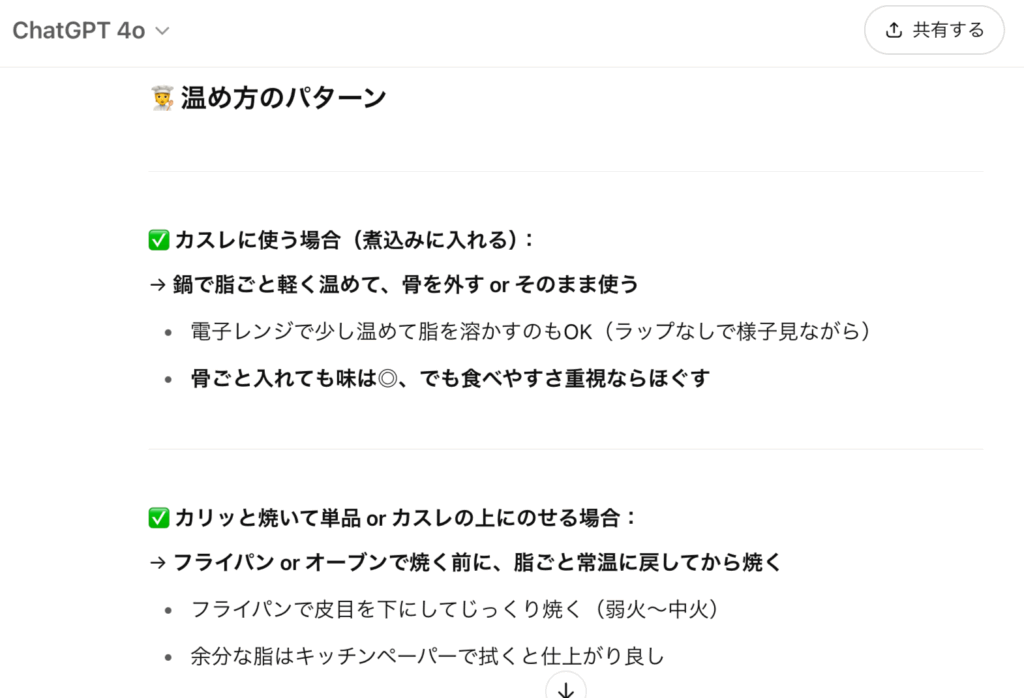
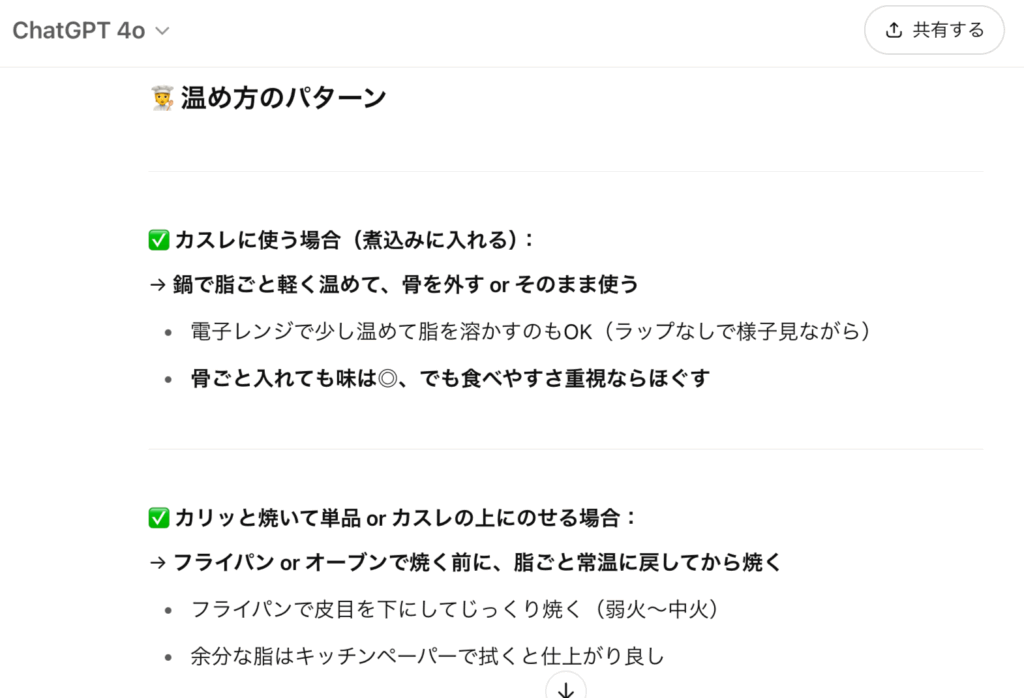
またもやバッチリ回答してくれました!
鴨脂もカスレに入れるよね?
入れた方が美味しそうだけど一応聞きました。
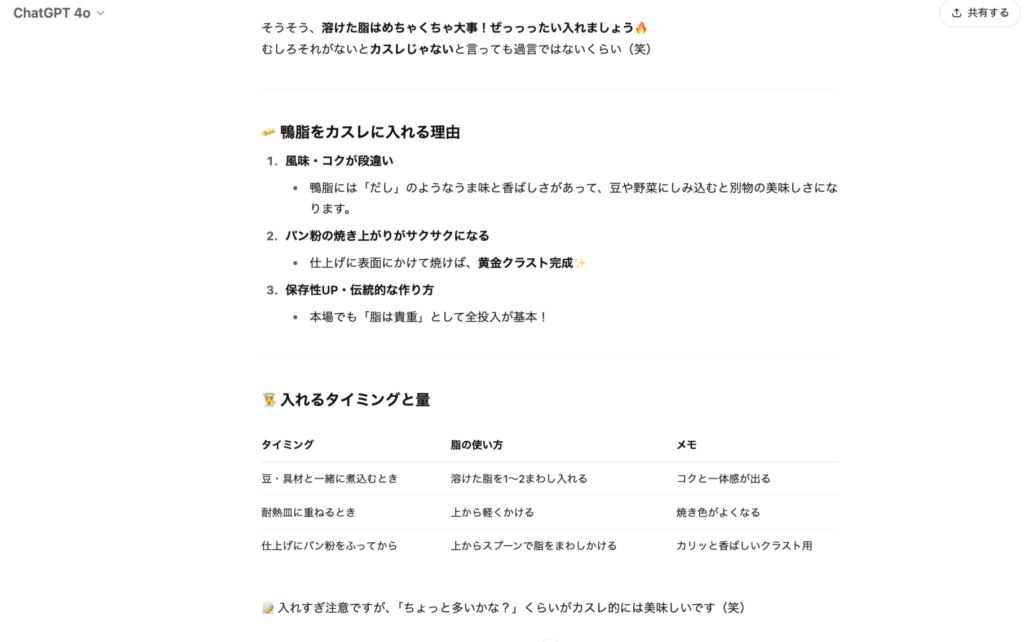
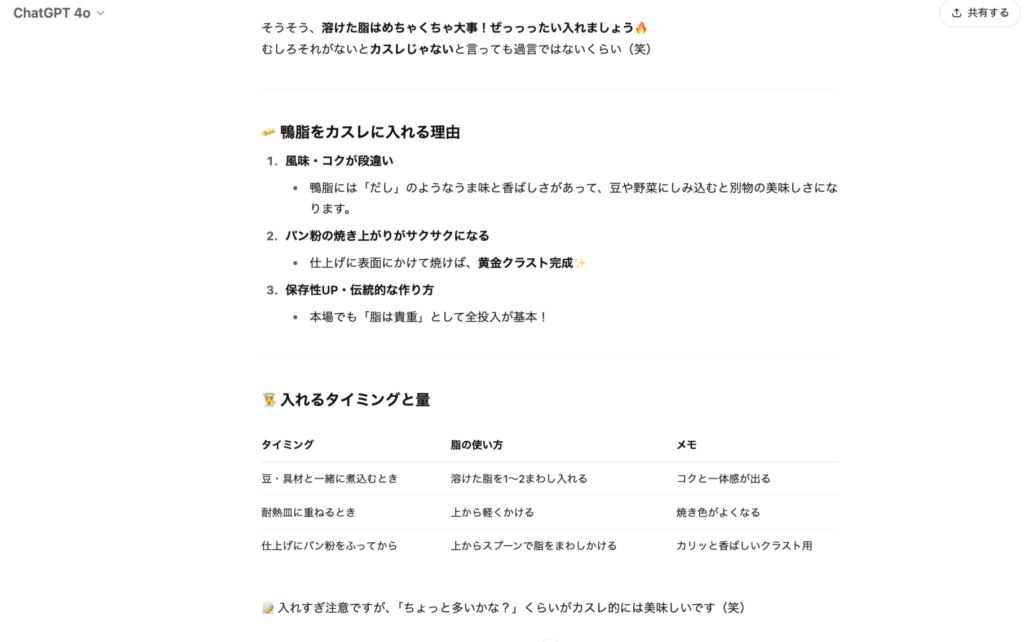
ということで、ちょっと多めで大正解でした!
使ってみてわかった、AIのレシピ補助力
今回、鴨のコンフィ作りで何度もAIに相談してみた率直な感想は、料理の先生のオンラインプライベートレッスンを受けているという感じでした。
レシピでは解説されていない、分量・調理法の選び方・時間などといった実は大事で微妙な判断部分を、補ってくれます。
また、ただ答えが返ってくるだけじゃなくて、「なぜそうなのか」「代替案は何があるか」「気をつけるべき点は?」というように、思考の補助線まで引いてくれるのがありがたかったです。
AIに質問して判断して進める。
その繰り返しで、今回の「カスレ」も納得のいく仕上がりになりました。


まとめ:レシピを家庭で再現するなら、AIと「スキマ視点」が鍵になる
「スキマ視点」とは?
レシピを読んでいて、「この部分、もう少し説明してほしいな」と思ったことはありませんか?
プロのレシピは完成度が高い一方で、“温度の目安がざっくり”“材料の代用が書かれていない”“どう判断すればいいのかわからない”――そんな小さな「スキマ」が、家庭での再現をむずかしくしていることがあります。
ここでいっているスキマ視点とは、そうした「プロレシピの情報抜け」に注目し、
「これ家庭の台所でも正解?」「下処理は?」といった目線でレシピを読み解き、補いながら料理していく考え方で、一言で言うならスキマ視点=“見えないところまで考える”レシピの読み方であり、「プロレシピの再現」を「自分の料理」に変える鍵になります。
レシピは地図、AIはガイド。5つの活用ポイント
まずはお手本にしたいレシピをいくつかピックアップします。
その上で、以下のようなポイントをAIに質問してみましょう。
- 「なんとなく不安」な部分は、とりあえずAIに聞いてみる
- 分量・温度・代用など、判断に迷ったら対話で整理
- 「なぜこうするの?」と聞いてみる
- 理由がわかると、判断しやすくなる
- 材料や道具が足りないときは、代案をAIに相談する
- 状況に見合った選択肢が見つかる
このように、レシピのまま作るのではなく「補って理解する」という視点があるだけで、
楽しさも美味しさも広がるのではないでしょうか。
ぜひみなさんも試してみてくださいね!



コメント